ある日、自分がゲイだと気づいてしまったらあなたはどうするだろう。
妻も子どももいて幸せな家庭を築いている、ごく普通の日常で。
一人の男性に出会い、同性愛者となったロブ。妻子持ちで、人生も半ばの頃。
妻に打ち明け、訴えられ、会社も追われ、貯金も何もかもを失い、それでも自分を偽って生きることをやめて残りの半生をゲイとして生きた。
これは、ロブに出会い最後の数年間をともにした恋人の、日記をもとに書き起こした実際の手記だ。
▶︎前編へ

8ヶ月前
ロブが、遂に退職した。彼はNPO法人で最後の10年間を勤めきった。組織体系が変わりはじめ、ちょうどやめ時だと感じたらしい。シニアモデルにでもなろうかな、などと冗談を言っていた。
彼はいつだって目立っていた。彼の大胆な話や溢れでる人間味に惹かれてしまうのだ。これが、ぼくが彼を愛するようになったたくさんある理由のうちの一つだ。「どう思う?」大きな白い歯をむいてにかっと笑いながら聞く。「スーパーモデルにならないわけないだろう?」
彼は10代の頃からずっと働いていた。初めての仕事は、コネチカットの叔父の靴屋。ロブは配達員をしていて、店の在庫を靴屋やセールスマンに届けるのが仕事だった。大学を出たあとは小学校の教員になり、結婚して3人の息子に恵まれて、コネチカットで幸せな家庭を築いていた。
1970年代初めの頃だったという。数年教員を務めたあと、出版会社で児童向けの本の編集者へと転職した。さらに数年働き、小さな自分の出版会社をはじめた。この時、ロブは浮気をしていた。同僚がロブに好意を持ったことからその関係ははじまり、数ヶ月続いたという。
そして、その同僚はゲイだった。これをきっかけに、ロブは自分自身がゲイだったと気づいた。この先も自分はずっといい夫であり父親でいるのだと思っていたから、こうなるなどまったく想像できなかったことだと、ロブは話していた。
それから数年、ゲイであることを隠しながら生きていたが、ダブルライフに耐えきれなくなったところですべてを告白した。家族は崩壊した。彼のかつての妻は彼を訴え、彼はすべてを失った。会社も、貯金も、家も、それから親権も。本当に、すべて、だ。
その時の裁判員がホモフォビックだったから、結果は最悪だった。人生をいちからやり直しだ。ロブの父親が、彼を家に呼び戻した。援助を申し出た。ロブがゲイであることを気にせず、昔と変わらず愛してくれた。
「おれの父親をきっと気に入るよ」。ロブはそう言った。「偉大な男で、偉大な父親なんだ」
その後、彼はマンハッタンに移り住んだ。70年代終わりのことだ。彼はそこでパートナーと出会い、数年を共にしたという。彼はたくさんの恋人にも友人にも出会ったが、同時にその多くをエイズで失った。80年代のこと。ぼくはというと、そのときちょうど20代前半で、ゲイであることをカミングアウトしたばかりだったから、エイズに苦しむゲイの世界のことなど知るはずもなかった。でもロブは、たくさんの近い友人がばたばたと死んでいくのを、目の当たりにしていた。
9ヶ月前
ぼくは、ロブがクリスマスのフルーツケーキを作っているところを撮ったショートムービーを作った。ぼくの父親もよくフルーツケーキを作ったが、大嫌いだった。歯が痛くなるほど甘ったるい。
それに比べて、ロブのレシピでできあがるケーキは全然違った。さっぱりしているのにバターが濃厚でおいしい。でもきっと、最大の理由は「ロブがぼくのために作ってくれたから」なんだろうと思う。
材料を用意しているところからiPhoneで録画した。彼のイタリアの家族の秘伝のレシピだという。キッチン用具も、いくつかは母親から譲り受けたものだと言っていた。「あっちにやってくれよ、そのカメラ!」と、彼がナッツを細かく刻んでいるところをクローズアップしていたら不機嫌な顔をしていた。一部始終を撮って、その後編集し、DVDに焼いてロブの息子にクリスマスディナーのおまけとしてプレゼントすることにした。
当日、ぼくは寒いからと嫌がるロブの息子たちを引き連れてバルコニーに出て、「多分笑うと思うんだけど」と、包みを開けて見せた。「これは、君たちの父親がフルーツケーキを焼いているところを撮ったんだ」。そういうと、彼らは顔を見合わせて、「多分そのケーキ、まずいだろう」と。「大事なのはケーキ自体じゃなくて、家族のことなんだ。これを残しておきたかった。いつか君たちの父親がいなくなっても、今度は君たちがまた将来の息子たちに同じケーキをつくってあげられるだろう」。熱くまくしたてるぼくを横目に、凍えながら、早く戻りたい、早くお酒を飲みたい、と部屋の中をしきりにちらちらと見るばかりだった。
1年前
イタリアへ向かう途中、ぼくたちはニューヘブンに寄ってランチを食べようと「フランクペッパーピッチェリア」に居た。ロブは、ここのホワイトパイというクラムとチーズが包まれたクラシックなパイを絶賛していた。確かに人気の店であることは、長蛇の列からわかる。昔ながらのダイナーのようで、遠い時代に来たような気持ちになる。
やっと席に座れたのは1時間程待ってからだった。ロブはグルテン嫌いにも関わらず、ピザを2枚も頼んでいた。彼はかつて彼の両親がロブとその兄弟をこのレストランに連れて来てくれたんだ、と話す。その後で、ぼくたちは墓地に行き、ロブの両親に祈りを捧げた。ロブは墓石に膝まずき、ゆっくりと十字を切り、静かに涙を流した。ぼくは彼の側に寄って、そっと肩を抱いた。
2年前
ぼくたちは、ロブの2番目の息子の家にいた。クリスマスディナーに呼ばれたのだ。ロブは「心の準備はできたか?」と聞く。ぼくたちはまだ車の中にいた。「うまくやれそうか?」
「もちろんだよ」。ロブに笑いかけた。
ロブはぼくに、クリスマスディナーがいかにカオスかを何度も警告していた。誰も彼もがぎゃーぎゃー騒ぎ、子どもたちは叫びながら走り回る。両親たちはそれを止めようとうろうろ。男性陣はバックヤードに煙草を吸いにいそいそと出て行く、と。
その通りのディナーだった。ぼくは、自分の親戚たちを思い出した。同じくらいうるさくて、カオスで、動きっぱなしのディナー。これが家族だ。ぼくはテーブルの向こう側にいる誰かに、笑顔で叫んでサラダを渡した。
26ヶ月前
ぼくたちはディナーを食べていた。この日もまたロブがイタリアンの腕を振るってくれた。いつも通りおいしい。
「知ってるか?」ワインを飲みながら、ロブははじめる。「お前はおれよりも長生きする。これは決まっていることだ」。真剣な顔を向けた。「だから、少しずつ、準備をしなくちゃいけないね」とロブは言う。もう選択はしてしまった。何が起こっても、ぼくは彼の側にいるのだ、と。
「次を考えなくちゃいけないんだ」と、今度は煙草をもてあそびながら言う。「誰か違う人を見つけた方がいい」
ワインが空になった後で、ぼくは片付けをし、全部ディッシュウォッシャーに突っ込んだ。既に選択はしてしまったんだよ、ともう一度自分に言う。

28ヶ月前
ぼくは、ロブと住みはじめた。ロブのアイデアだった。互いの家を行き来しはじめて1年くらい経つ頃、もうほとんどロブの家に住んでいるようなものだった。服を取りに帰るだけになっていたから、ぼくの部屋はもはや高すぎるクローゼットでしかなかった。家具は捨てたり譲ったりして、所有物の9割は手放した。これは、ぼくたちにとって大きな一歩。ロブはもう長い間人と住んでいなかったし、ぼくにしても誰かと暮らすのは20代の頃ぶりだ。
初めはうまくいかなかった。互いの変わった癖に馴れなくてはいけなかったし、ぼくは歴史のつまった彼の所有物だらけの部屋に馴れるのにも時間がかかった。けれど、結局ぼくたちは馬が合うようだった。それぞれの二つの日常が、一つの部屋に自然に溶け込んでいく。
ぼくたちは恋人同士だった。うまくいく日も、そうでない日もある。普通の恋人たちと同じように。時々、まるで二つのボルケーノが一度に来たような壮大なケンカもした。どうにかして相手を打ち負かそうとした。それでも結局いつの間にかマグマは冷えて固まる。その後は決まって、最高のセックスをしたんだ。
30ヶ月前
ぼくはロブの元妻の親友の隣に座っていた。ロブの一番下の息子の結婚式が、ロンドンで挙げられたのだ。この息子に会うのはこれが初めてだった。それは小さな結婚式で、ぼくはその親友と隣り合わせた。元妻も、別のテーブルに居た。「彼女に好印象をあたえなくては」と思った。ぼくは、ロブと元妻のあの悲惨だった歴史の一部ではないし、自分がロブの何だ、というよりぼくという人間を見て欲しいと思った。
その後(何杯か飲んで)、とてもいい時間を過ごし、その親友はぼくを気に入ってくれたようだ。彼女は元妻にもぼくのことを良く伝えてくれたみたいだ。それがきっかけで、この式の終わりに、ぼくは冗談も言えるほどに元妻と会話を楽しんだ。ロブはそんなぼくらを少し離れたところから見ていて、自分のグラスを掲げ、ぼくに笑いかけた。
31ヶ月前
ぼくたちはブルックリンのグリーンポイントでそわそわしながら待っていた。ロブの2番目の息子が家族を連れてやってきて、ディナーをすることになっていた。彼らに会うのは、これが初めてだった。
遅刻を詫びながらようやく彼らが現れたとき、彼の息子の子ども(ロブの孫)は、ぼくを不思議そうに見つめていた。「この人、誰なんだろう」と思ったのだろう。ロブは彼らを一度少し離れたところに呼び、前の恋人とどうなったのか、そしていま、彼の人生にはぼくが居るのだということを説明していた。ロブの義理の娘とは、90年代にニューヨークのよく行ったクラブシーンについて盛り上がった。恐らく、何度か同じヒップホップのパーティーに居合わせていただろうとわかったときは大騒ぎだった。彼らはぼくよりも少し若いくらいだったので、たくさんの共通点があった。
ぼくはロブの息子が、ロブに親指を立て頷いているのが目に入った。ぼくを選んだロブに「やったな」と言ったのだ。
33ヶ月前
「一体どこに向かっているんだ」。「内緒だよ。もう少し待って」とぼくは濁す。「あと数分でわかるから」
ぼくはウィリアムズバーグに車を走らせていた。お目当ては、イタリアンストリートフェアだ。車を少し離れたところに止め、歩いてそのストリートフェアに向かう。ロブがイタリアン好きだから、初めてのデートにはもってこいの場所だと思ったからだ。人でごった返すストリートを抜け、協会の前にたどり着いた。
「まいったな!」ロブは驚きを隠せないでいた。「この教会、おれが育ったコネチカットにあったのと同じだ!」。ぼくたちは教会の周りをゆっくり見てまわった。ロブは12もある像すべての名前を言ってみせた。ぼくはカトリックだけれど、聖徒の名前すら言えないので感動してしまった。ロブは笑いかけ、ここに来れて嬉しい、懐かしい日々を思い出す、と笑いかけた。ぼくは、一生懸命その像について勉強した。
車に戻るまでにぼくたちは砂糖がたっぷりかかったイタリアンケーキを買って、わけあった。
34ヶ月前
ロブが恋人と別れたようだ。ぼくたちが初めて会い、三人でセックスをした夜から、こうなるんじゃないかと予感していた。あの夜、二人の関係を、ぼくが少し変えたことを感じた。三人でのセックスは、とても情熱的だった。しかし、その恋人が部屋から出ていったあと、ぼくとロブはなんだか違ったエナジーが湧いてきた。
これが後に何をもたらすだろうかもわかっていたし、もちろん二人の間に割って入りたいなど思っていたわけではない。だから、その夜を最後に、少し距離をとるようにした。それでもロブはぼくに電話したりメールをくれたりと、もう一度会うとした。彼の恋人も含めて三人で、だ。ぼくは、もう一度三人で、とは考えていなかったから、丁重に断った。メールだけは続けていて、互いをよく知っていった。メールを通して、ぼくはこの男に惹かれていった。
3年と半年前
ぼくは、独り身だ。そして今日は誕生日だ。友人が食事やバーに誘ってくれたけれど、一人で横になっていたい気分だった、なんとなく。
数ヶ月ほど交流している男性がいた。彼の名前は、ロブ。ハンサムで年上だ。彼の言う年齢が本当だとしたら、父親にあたるほどの年の差だ。まだ一度も会ったことはなく、ぼくたちは出会い系のオンラインサイトのチャットのみで交流していた。
彼は自分には恋人がいて、もしぼくたちが体の関係を持つとしたらそれは三人でだね、と言っていたのを思い出す。うん、今日は誕生日だし、と思い立つ。そして、ぼくは彼のその言葉に乗ってみることにした。彼の住所を聞き、さっそくその夕方から会うことにした。
数時間して、ぼくは彼のアパートに着いた。彼の恋人がドアを開けてくれた。彼もハンサムだ。けれど、そんなにタイプでもない。ぼくは、ロブに会いにここに来たのだ。ロブはソファに腰掛けて何か飲んでいた。恋人がぼくに、スコッチは、と尋ねたので、もらうことにした。
「座ったら」と、ソファをあけてくれた。ぼくはその日、なんだかシャイで、どうしてだかはわからない。ロブはぼくをみて、挨拶のキスをしてくれた。そしてぼくも、ゆっくりとキスを仕返す。彼に笑いかける。ロブも、それに応える。ゆっくりとスコッチを飲みながら。彼はぼくの手に触れる。ぼくはもう片方の手を重ねた。彼は、ぼくの手を強く握り返す。ぼくは、この誕生日が特別になる予感がしていた。
おわり
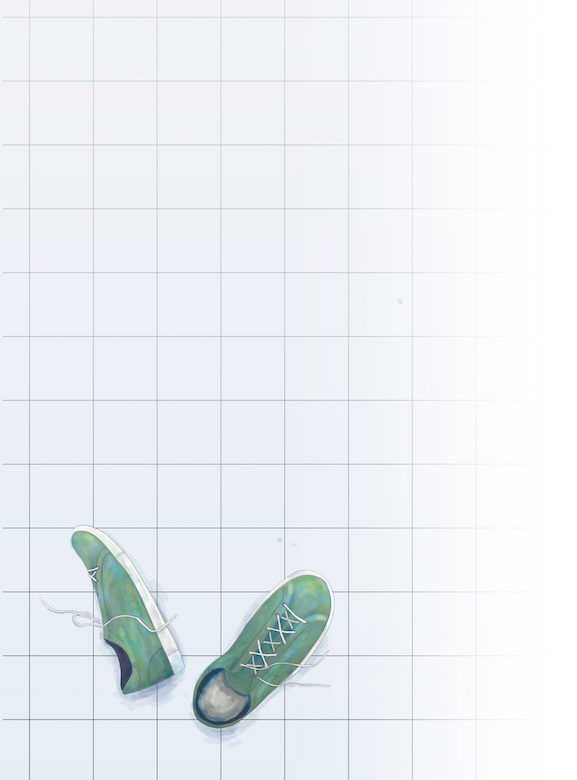
—–
Original Release HEAPS Issue 17, edited on Jan 2017
Illustration:Miki Ishikawa
Translation:Sako Hirano
















