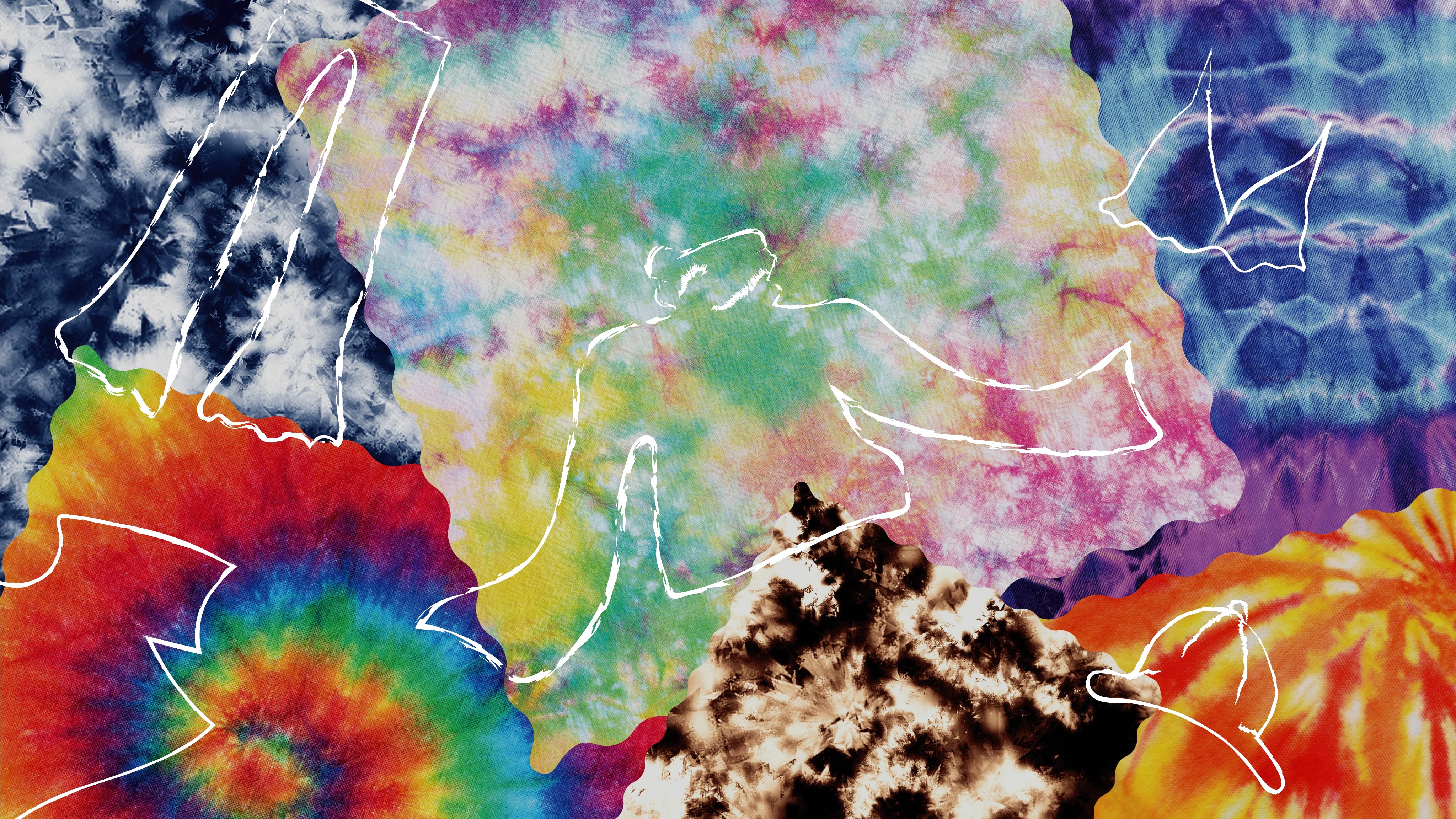紐などで”縛る”を意味する「tie(タイ)」と、”染める”を意味する「dye(ダイ)」を合わせて「tie-dye(タイダイ)」。この日本語で言うところの「縛り染め」のTシャツやパーカーらが、世界各国で長らくトレンドになっている。特に2020年は、流行に敏感な人に留まらない広がりを見せ、タイダイがサブではなくメインストリームになった年だった。一体、タイダイの何が人を惹きつけたのか。2020年の空気感と何がどのようにリンクしていたのか、を考えてみたい。
世界的なトレンドになったタイダイとヒッピームーブメント
服なんてその日、その時の気分で選べばいい——のだとしたら、その日、その時の気分とは何なのか。
なんとなく「タイダイを着たい日」というのがあるのだとしたら、そしてその日がウッドストック・フェスティバル、もしくは同系の野外フェスティバルではないのだとしたら、一体、その日はどんな日、どんな時期なのか。
2020年の雰囲気を振り返るうえで、新型コロナウイルスの世界的大流行(パンデミック)と、5月末のジョージ・フロイド事件を機に各地各界に広がったBLM(反人種差別運動)は欠かせない。この二つは時代の潮流を変えた非常に大きな出来事だった。そんな時代の分岐点の中で、「タイダイ」の流行はピークを迎えていた。
タイダイのスウェットを上下で合わせるスタイルはパンデミック中に広がった新しいトレンドだったかもしれないが、タイダイそのもののルーツは数百年前に遡る。
タイダイはテキスタイル・デザインとして最も古く、最も普遍的な手法の一つだといわれている。特定の地域・民族の間でのみおこなわれてきたのではなく、アフリカ大陸からアジア、アメリカ大陸に至るまで、世界中のさまざま地域・文化の中で、実に600年以上にわたって実践されてきた。その意味で、タイダイは「異なる文化の中にも類似点が存在する」ということを教えてくれる存在だ。
そんなタイダイが、はじめて世界的な「トレンド」になったのは1960-70年代。アメリカでヒッピームーブメントが巻き起こった時代だ。制度に縛られず、自由に生きることを志し、人類の愛と平和を訴えたヒッピーたちの間で、タイダイは暗黙のユニフォームになり、また、彼らが中心となったDIYやカウンターカルチャーのシンボルになった。マスメディアによって喧伝される流行や大量生産による画一的な既製服を拒否し、個性的なファッションを追求するアンチ・ファッションの姿勢も含んでいた。
カウンターカルチャーの象徴化にあった、染料ブランドの資本主義的マーケティング
ところが、タイダイが「DIY」や「カウンターカルチャー」のシンボルになったきっかけを探って行くと、そこには資本主義的な巧妙なマーケティング戦略があったという事実にぶつかる。2020年のタイダイの流行を考えるにあたって、もう少しこのトレンドの歴史について述べたい。
その戦略を講じたのは、アメリカの染料メーカー「リット(Rit)社」だ。同社は、液体染料と資金を複数のアーティストに提供し、手染めのシャツを作らせ、ウッドストック・フェスティバルで売るように頼んだのだそうだ。同フェスティバルは、1969年に開かれた当時のアメリカのカウンターカルチャーを象徴する歴史的な野外コンサートである。

ウッドストック・フェスティバル。これは25周年として1994年にニューヨークで開催された時の写真。
1918年に創業したリット社は、箱に入った単色染め用の粉末染料を売る会社として知られていた。しかし、第二次世界大戦が終わり、大量生産・大量消費へと時代が移り変わる中で、苦戦を強いられていた。それまではドレスやシーツなどの布製品を自宅で染めていた人たちも、「新しいものを買う」という選択をするようになったからだ。
そんな時、当時のトップだったドン・プライスは、ニューヨークのグリニッジ・ヴィレッジ界隈に集まっていたボヘミアンやアーティストといった、 “クリエイティブ・タイプ” の若者に商機を見出す。まず、主力商品をそれまでの箱入りの粉末染料から、カラフルなデザインが手軽にたのしめるチューブ式の液体染料に替えた。そして、前述の通り、ウッドストック・フェスティバルで宣伝販売するために、ボヘミアン風のニューヨークのアーティストらに新商品の液体染料とお金を渡し、タイダイのTシャツを作らせたのだ。
フェスティバルではタイダイのTシャツだけでなく、液体染料も並べられ、リット社は見事にブランド再生に成功。と同時に、ウッドストック・フェスティバルを彩ったタイダイのTシャツは、テレビや雑誌を通して次世代の若者へと広がっていった。
さて、話を「2020年のタイダイの流行」に戻そう。前述の通り、タイダイがファッションとして初めて流行したのは60・70年代。以来、タイダイは、流行り廃りを経てきたわけだが、リバイバルするときは概ねいつも「ヒッピー・ファッション」としてだった。つまり、タイダイとヒッピーは対(つい)であり、ヒッピーに付随する「ラブ&ピース」「自由」「反権威主義」といったイメージは、タイダイのイメージ、そしてステートメントにもなっている。
そんなタイダイは、なぜ、2020年の空気感と共鳴したのか。DIY、政治、心理の3つの側面からみていきたい。
タイダイはポリコレに触れず。それでいて攻めているという具合
まず、DIYについては、外出自粛という異例事態だったことは大きく、自宅で楽しめることとして、パン作りやガーデニングをはじめたのと同じように「タイダイ(絞り染め)をやってみた」という人も多かったようだ。タイダイは、布を縛る紐と水、バケツ、染料さえあればできる、安価かつ敷居の低いDIYである。また、作るたびに仕上がりが異なる点や、どんな模様に仕上がるのかを完全に予測できない点も人を惹きつけた要因だったようだ。私も数回やったことがあるのだが、確かに、最後に紐を解いて広げるまで結果が分からないため、工程中は最後まで一種のドキドキが続いたのを覚えている。
次に、政治的側面については、タイダイの持つ「反既成政治」「反既得権層」や「不平等への抗議」といったステートメントへの共感の大きさが流行に繋がったように思う。特にパンデミックによる感染・死亡者数の多かったアメリカでは、被害者多くが低所得者、有色人種(特に黒人)であり、改めて不平等が明るみになったことも少なからず関係しているだろう。
5月末のジョージ・フロイド事件からの「BLM」が不平等に対する抗議を加速させていったのは周知の通りだが、不平等に対する厳しい目は、社会という大きな枠だけでなく、ファッションという業界にも向けられてきた。
表向きは「多様性」「インクルーシブ」を謳っていながら、業界や企業内部では有色人種に対する差別が横行していたこと、相変わらずの文化の盗用など、業界の「コロニアリズム(植民地主義)」は、パンデミック以前から問題視されてきた。
歴史上の偉人も「差別主義者だった」という理由で、その銅像は撤去され、名を冠した施設やイベントは改名される昨今は、「過去の〇〇を現代風に再解釈(したファッション)」というよくあるコンセプトも、内容次第である。
たとえば、過去の〇〇の部分が、「中世ヨーロッパの貴族の装い」だとしたらどうだろうか。
これを2020年の現代風のポリティカル・コレクトネス(政治的正しさ)を意識して解釈すると、少数の特権的な支配階級の人たちが労働階級者に低賃金で作らせた、という側面がどうしても際立つ。また、平等やデモクラシー(民主主義)と相反する「アリストクラシー(貴族制)」は、今日まで続く不平等の元凶とも考えられており、それを連想させる服が果たして2020年の空気感に合うのかというのは、着る側・発表する(ブランド)側の双方にとって、なかなかセンシティブな問題になっている。
一方、タイダイは、アリストクラシーやコロニアリズムの要素をほとんど含んでおらず、かつ、特定の人種・民族だけの伝統工芸ではないため、ほとんど誰が着用しても文化の盗用問題に触れない。つまり、ポリティカル・コレクトネスにほぼ触れることのない、ある種のリスクフリー・アイテムとも言える。それでいて、タイダイは、ロカビリーやパンクなどと同様に、若者の主張・意思表明のためのスタイルとして生まれた進歩的な側面もあり、社会に対して沈黙しているわけでも、攻めていないわけでもないという姿勢をみせることができる。「沈黙は暴力」とまで言われる時勢の中で、タイダイを採用するブランドが多かったことに決して無関係ではなかったように思う。
以前からタイダイを取り入れている新興ブランド。
感情の応急処置としてのタイダイ
「混乱の時代にはノスタルジックなファッションがリバイバルする」といわれている。つまりは、現実逃避欲や安心感を求める心の表れだったりするのだが、タイダイの持つ「ラブ&ピース」や「自由で開放的」なイメージも、コロナ禍の人々の心の隙間を満たしていたようだ。
「自由で開放的」とは、まさにコロナ禍で奪われたもの。「ラブ&ピース」も分断が深まったコロナ禍に著しく欠けていたものである。それらをタイダイを纏うことで、多少なりとも補っていたのかもしれない。
あるひとつの服装・スタイルというのは、理屈理論や宣伝やらだけで広まるものではない。人々が自分の目で「実例」を見て、「そうか、なるほど」という自分なりの納得があって、初めて世間一般に伝播するものだと思う。
60・70年代のアメリカという、人の価値観が入れ替わる混乱の時代に生まれたタイダイ。それは、既存のスタイルや業界への反対姿勢(アンチ・ファッション)の表明でもあった。しかしながら「リバイバル(再流行)する」ときには、黎明の頃に持ち得ていた“大きなものに対抗する進歩的な姿勢”は、もう本当の意味では存在しない。なぜなら、リバイバルとは、業界の「流行」の循環の中に多かれ少なかれ組み込まれてしまっていることを自ずと意味するからだ。
尖った姿勢までマルッと飲み込まれて、結局は業界の繁栄の肥やしとなる——。その意味でタイダイは、皮肉な運命を背負っている。
Text by Chiyo Yamauchi
Content Direction & Edit: HEAPS Magazine
【訂正 1/8/2020】
ウッドストックの写真キャプションの表記に誤りがあったため、以下の通り訂正いたしました。
※訂正前
これは25周年として1924年にニューヨークで開催された時の写真。
※訂正後
これは25周年として1994年にニューヨークで開催された時の写真。