「#MeToo」ムーブメント後に、米国で急成長しているウェブマガジンがある。扱うトピックは、おちんちんの話からメンタルヘルス、デジタルカルチャー、政治まで幅広い。そしてその編集長、米男性誌『プレイボーイ』の元編集者だ。探求するのは、「21世紀の新しい男性像」。社会の変化を受けて女性向け雑誌の内容が充実していくのに対して、「男性誌はというと、相変わらずだった」。
「女性誌に比べて、時代の変化を汲み取れていない」フラストレーション
ジェンダー観は、時代や社会によって変わるもので、時代が変われば求められる「男らしさ」と「女らしさ」も変わっていく。以前、「#MeToo」時代に葛藤しているのは女性だけでない、男性もであると増加する米国での「男性の集い」を取り上げたが、時代の変化を敏感に感じ取り、それにどう対応すべきかに苦慮する男性は、やはり少なくない。
「#MeToo」の気運を胸いっぱいに吸い込み、昨今のフェミニズム議論をきっちり煮詰める女性向けのマガジンが充実していくのに対し、男性向けのものはというと「相変わらず」。
「正直、僕はフェミニスト・デジタルマガジンの『Jezebe(イゼベル)』や、現代のジェンダー観やアイデンティティに切り込む『Broadly(ブロードリー)』などのコンテンツをみては、嫉妬していました」。
取材にてそう話すのは、ウェブマガジン『MEL(メル)』の編集長ジョッシュ・スコールメイヤー氏。同誌は米国で急成長中の男性向けのマガジンで、読者数は「#MeToo」ムーブメント開始後の17年末から18年夏までに2倍増へ。現在、一ヶ月あたりのユニークビジター数は、250〜350万人を誇る。
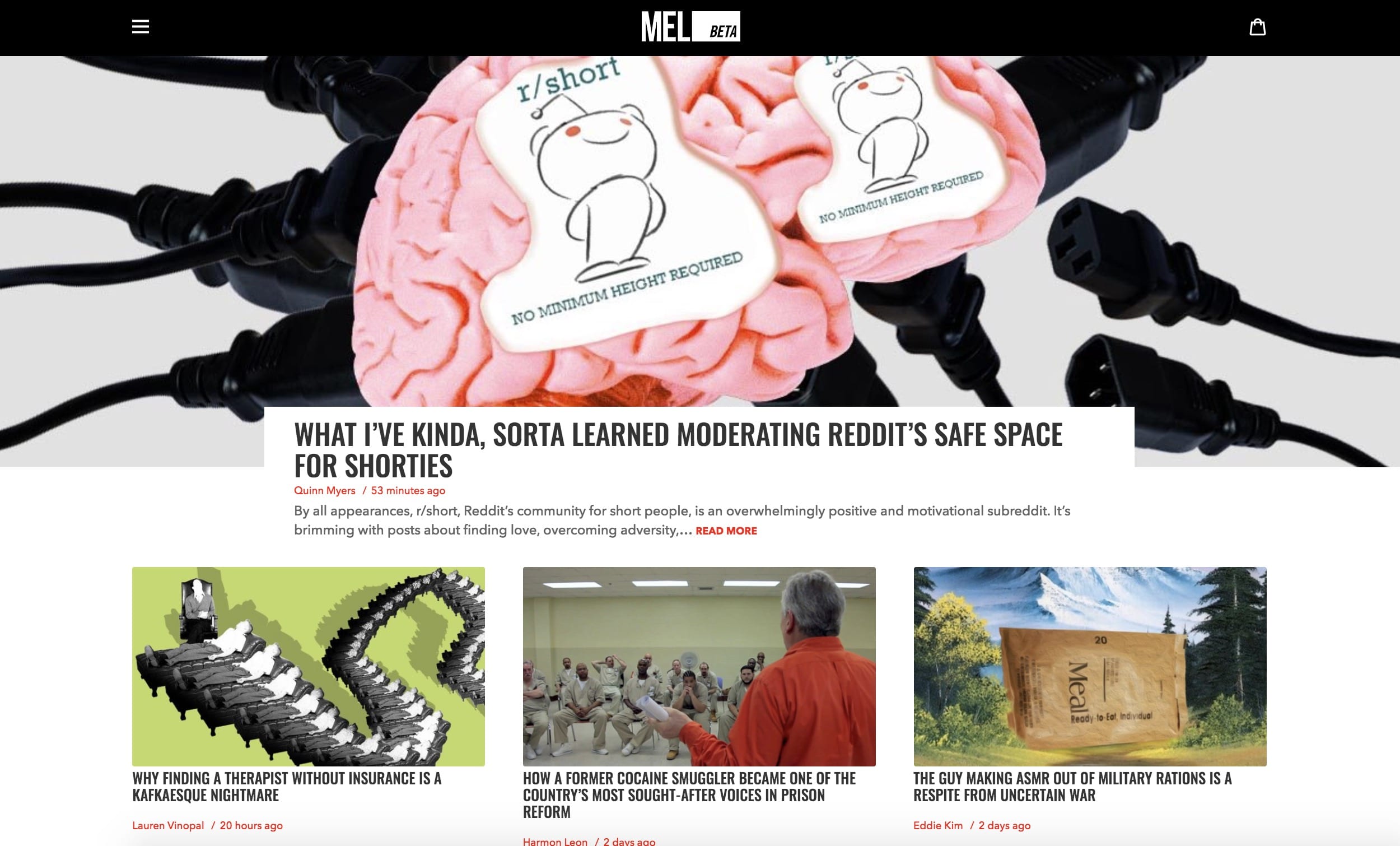
メルは、現代の男性の視点で作られたライフスタイル・カルチャー誌だが、「“理想”の男性像を押しつけるものではなく、等身大の人間について語るもの」だとジョッシュ。つまり、こんな服を、こんな体型で着こなし、この季節はこんな旬のアクティビティを嗜むのが男だ、カッコいい、イケている——といった話はしない。
その感じ、聞き覚えがあるなと思ったら、93年からフェミニズムをポップカルチャーとして届けてきた『BUST MAGAZINE(バスト・マガジン)』の編集長が、取材にてまさに同じようなことを言っていた。「女らしさ」「男らしさ」といった既存のジェンダー観からの脱却を目指すときに、はたまた「マスメディアにはない情報」を報じる役割を担うときに、新しいメディアがとるべく姿勢は、まずは(有害な)理想像を押しつけるのをやめて、現実についてきちんと語ろう、であり、そこに性別は関係ないのだろう。実際、「男性の視点で作られた、とは言ってみたものの、編集部には女性もいますし、“男性らしさ”については模索中。飽くなき探求を続けている」と話す。
メルのカテゴリーは「カルチャー」「ワーク」「ヘルス」「リレーションシップ」「ディック」の5つに分けられている。アクセス数がもっとも多いのは「ディック」。そう、おちんちん関連のトピックで「ディックを大きくするためのコーチを雇ってみてわかったこと」「ウェアラブル・バイアグラって、結局なんだ?」といったタイトルが並ぶ。読者層は20代ー50代と幅広く、コアは25〜45歳だ。「ディック」ネタが一番人気の“男性向け”雑誌ではあるが、意外にも「読者の35〜40パーセントが女性」。性別問わずに読者を増やしている理由は、「わかりやすさと学術的な正確さを両立させているから、ではないでしょうか。タイトルは、おもしろおかしくしていますが、中身は、独自の取材を通したジャーナリズムや考察記事で、長文記事が多いですし」。
編集長のジョッシュは、2014年までプレイボーイの編集者を務めていた。時代の変化につれて、いくら広告関連とはいえ「高級ソックスを履きこなしてこそジェントルマンだとか、そういうのを書くのに違和感を覚えていた」と話す。
米プレイボーイ誌の名誉のために言っておくと、同誌といえば女性のヌード写真の豪華さしかり、エロ雑誌のイメージが強いかもしれないが、実は文字のページも少なくない。中にはジャーナリスティックな視点を持った読み応えのある記事もあり、インターネット普及以前は、たんなる性的刺激、エロ目的であれば、プレイボーイより文字の少ない『HUSTLER(ハスラー)』を選ぶ男性が多かったと思われる。
そんな米プレイボーイ誌にいたジョシュが、次のステージで目指すのは「男性の心の隙間を埋めるような」感情や思考など、内面にフォーカスした男性向けのプラットフォーム。かといって、まじめな自己啓発セミナーのようなものではなく「ユーモアを軸にした」前のめり過ぎないものだという。
「男らしさ」に困惑する等身大の男性を自虐ユーモアで描く
メル・マガジンの発行や運営についても触れたい。発行元は、「ダラー・シェイブ・クラブ」という月額1ドルからの髭剃り替刃のサブスクリプションサービスを提供する髭剃りブランドの企業。つまり、メルは一時期急増したオウンドメディアだが、あくまでも「独立した雑誌」で、ダラー・シェイブ・クラブの広告は一切出てこない。購買数や認知向上の目標も追っていない。「独立系だからこそ自由にやれる。それがメルの強み」だと話す。創刊は2015年。当初は週に2回のニュースレター配信で、その後、ミディアムをプラットフォームにしていた時期を経て現在に至る。
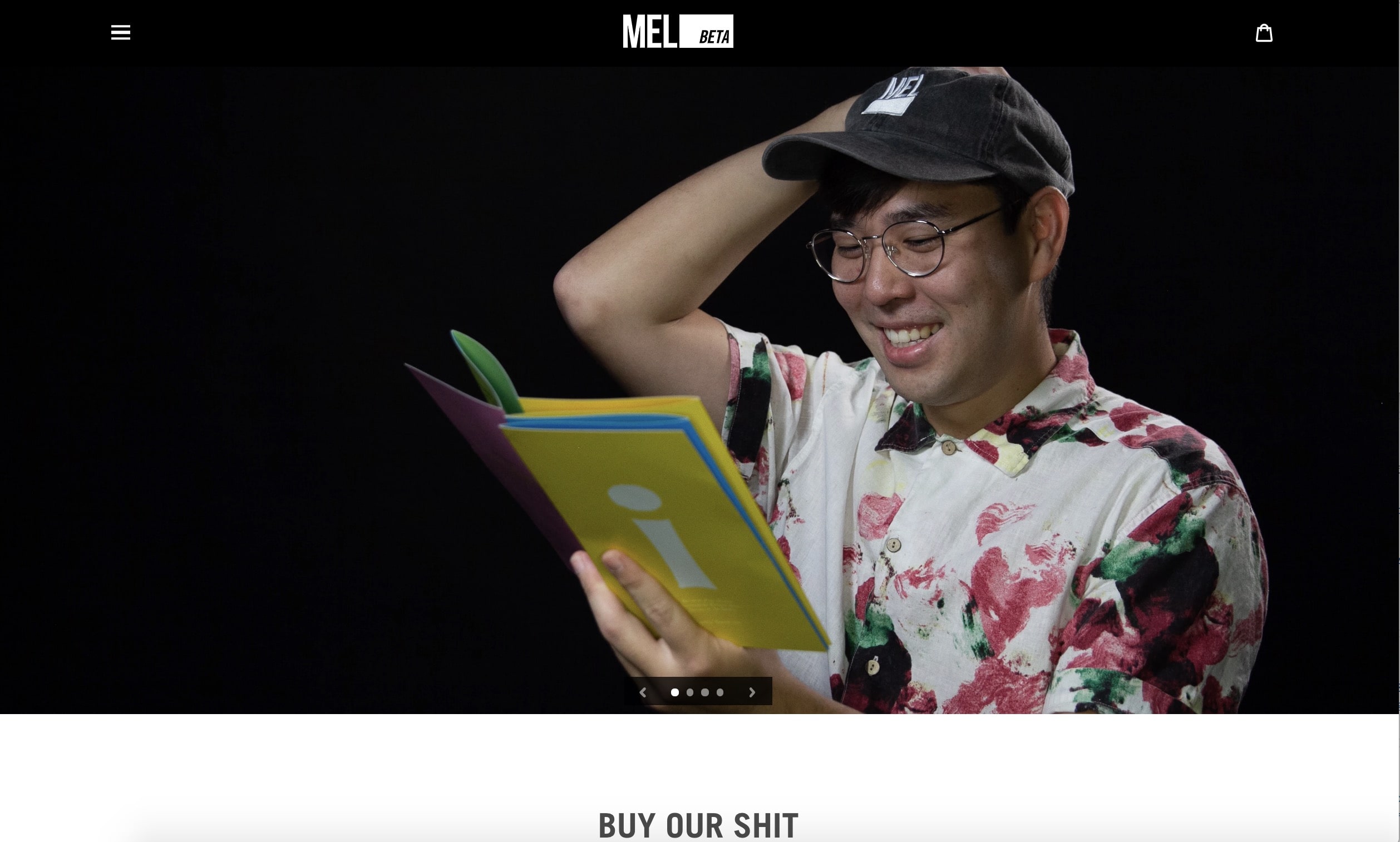
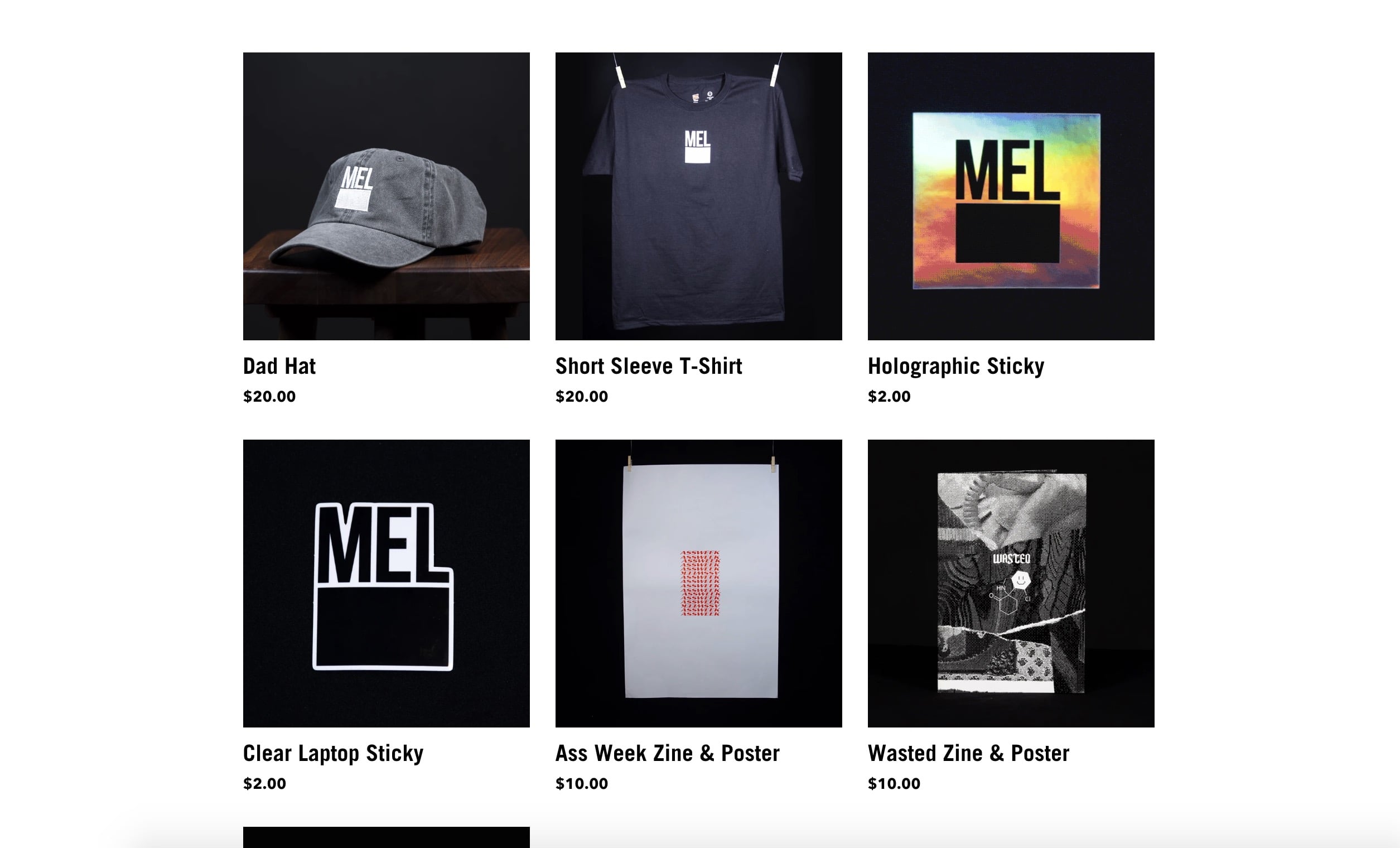
(出典:MEL MAGAZINE)
ここで少し、ダラー・シェイブ・クラブについて説明しておきたい。同社は2011年創業のスタートアップで、少数の主力ブランドによる寡占状態が一世紀以上にわたって続いていた髭剃り市場に、“風穴を開けた” ことで知られる。
16年には顧客数が約300万人に到達。その後、世界有数の巨大メーカーであるユニリーバ(Unilever)に10億ドル(約1140億円)で買収され、べンチャーキャピタルから支援を受けたスタートアップとしては、もっとも大きく成長遂げたブランドのひとつである。
その成功には、当時はまだ新しかったダイレクト・トゥ・コンシューマー(D2C)のサブスクリプションを用いたビジネスモデルもあるが、やはり「男の髭剃り」のイメージを一新したことが大きい。
それまでの男の髭剃り広告の定番といえば “マッチョ” であり、一世紀以上もの間ずっと、筋肉質な男性が、まさに筋肉のごとく凝り固まったな強さ、タフを賛美するマッチョイズムを提示してきた。
ところが、ダラー・シェイブ・クラブの動画に登場するのは、半裸のマッチョのハンサムではなく、オフィスルックの野暮ったい男性だ。「等身大の男ってこんなもんだべ」と言わんばかりに、男性の滑稽な一面を同社CEOがコミカルかつ自虐的に演じている。「ぶっちゃけ20ドルもする10枚刃はいらない。クオリティのよい1、2枚刃で十分」というメッセージは、コスパ重視の消費者に刺さった。12年に公開されたこの低予算動画が視聴者の共感を集め、同年の米アドエイジ誌によるバイラルビデオアワード賞を獲得。現在までに2,600万回以上再生されている。
等身大の男性のあか抜けない様を自虐的かつコミカルに描くダラー・シェイブ・クラブの世界観と、生殖器の話を「セックス」でも「ピーナス(ペニス)」でもなく、「ディック」でいくメルの世界観には、重なる部分が大きい。その共通する世界観の中心にあるのは、「男性らしさ」の固定概念からの脱皮と、自虐的なユーモアだ。
メルの副編集長のアラーナ氏(ちなみに女性)は、メルがユーモアを大切にしている理由について、こう語る。「男性には、自分の気づきや関心事、悩み事を、まるでこの世の一大事かのようにシリアスに考える人が少なくないですから」と、真面目でナルシストになりがちであることを指摘する。
もちろんシリアスになることが悪いわけではない。ただ、一歩引いて俯瞰してみることができるようになると生きやすくなるのも事実。「押しても引いても動かない。そんなときほどユーモアが効く。対立ではなく仲間意識を育みたいときもです」
商業ブランドの新しい雑誌のあり方
ブランドや企業がメディアに着手するケースは増えたが、メディアの中でも、比較的収益に繋がりにくい、広告を極力入れない入れない雑誌に着手することにメリットはあるのだろうか。それについてメルは「こうすれば収益につながるという明確なロジックはない」という。
「ブランドを支えるもの」には、いうまでもなくそれを支持する顧客の存在があり、企業としてはその裾野を広げていく必要がある。それには、キャンペーンやプロモーション広告を打つなどさまざまなやり方があると思うが、その一つとして、ダラー・シェイブ・クラブは、雑紙の編集者を雇いメルを発行している。
メルの存在意義は「新しい男性像の思想やジェンダー観を模索」し、メディアとしてそれを広め「共感する男性たちの心の隙間をうめること」。そして、その視点に気づいたり、価値観に共感したりする現代人が増えれば、同じように新しい男性像を提唱するダラー・シェイブ・クラブを選ぶ顧客も増えるだろう、という未来への投資の発想だ。
こと足早に社会のあり方が変わっていく現代においては、まずはその社会のひだを「見える・わかる」を育てていく存在としての雑誌は、新しい雑誌のあり方の一つではないか。メルというカルチャー誌は、ダラー・シェイブ・クラブというブランドが持つ文化資本でもあるのだ。
Interview with Josh Schollmeyer
Top image by Midori Hongo
Text by Chiyo Yamauchi
Content Direction & Edit: HEAPS Magazine
















