ついに契約へ。分厚い札束を持ち、A不動産へ
2021年を迎えた。香川県は例年に比べ、温かい冬だった。私は初詣にでかけたとき、手を合わせ家族や友人の平穏と「モスク建立がうまくいきますように」と、神前の祈りの中にひそめた。一方、フィカルさんたちは日々の祈りを繰り返した。寄付の集まり具合が気になってしょうがないだろうが、浮足立つことなく、静かに運命に身をゆだねていた。
その噂を聞いた数週間後、私は香川県のx市にいた。グループのリーダー、フィカルさんに会い、家にあがったその日から、当初の想定よりもだいぶ重く、深く、そして親密に、計画の渦中に身を置くことになった。
この連載では、フィカルさんと仲間たちがさまざまな問題にぶち当たり、それでもめげず、時に迷走しながらも、モスクのために突き進む姿を追う。資金集め、物件探し、そのどれもが外国人の彼らには大難題だ。浮き彫りになる差別や偏見。仲間との不和。
地方都市で外国人が生きることはどういうことか? 信仰とは? なぜそこまでしてモスクを建てようとしているのか?
これは、香川県にゼロからモスクをつくろうと計画するインドネシア人ムスリムたちの、いざこざとどんでん返しと、そして愛と驚きに満ちた日々を追う現在も進行中のルポルタージュだ。
フィカルさんと出会って、1年が経った。その間に、私たちはお互いの悩みを相談し合う友人になった。だからジャーナリズムというよりも、友人とその仲間たちが夢を追う様子を記録したものという表現が近いかもしれない。
私とフィカルさん、そしてインドネシア人のムスリムたちとの出会いから今日までの約16ヶ月の道のりを、そしてその日々に私が目にし耳にし立ち会ってきた彼らのさまざまをレポートしてきたこの連載も、残り2話でついにひと つの章の完結へ。
第1話「出会いと、初めて足を踏み入れた日」はこちらから。
繋がりと絆を強める、場所も時間も超えたコミュニティ
1月、私はほかのことに忙しく、彼らと会う機会が減っていた。フィカルさんも、できることはすべて終え、あとは寄付が集まるのを静かな日常とともに待っていた。コロナで借り手がつく見込みのなくなった建物の値段を2,800万円にさげてくれたという、良い報告があったのもこの頃だ。
1月中旬に寄付の金額を聞いたときは、2,600万円。あと200万円か。ここまでくると感覚がおかしくなるが、200万円だってすごい金額だ。まだもう少し時間がかかるだろうと思っていた矢先の2月、何気なくひらいたアルムのSNSへの投稿が目に入った。私は驚いた。週に一度発表していた円グラフの色が、真っ赤に染まっている。英語で「目標金額に達しました! ありがとうございました!」と書かれてある。拍子抜けした。なにかもうひと悶着はあると思っていた。
急いでフィカルさんに連絡すると「そうね。ついに貯まりました」と言うだけだ。もっと感動的に喜びを爆発させたり、泣いたりするのかと期待していたのだが。嬉しくないのか? と聞くと「まだまだ安心できないね」と、まったく浮かれていない。できるだけ自慢しない、という謙虚さを大切にする宗教だからという理由もあるだろうが、彼にはここからがまた大仕事であり、疑心暗鬼に陥っていたのだ。
フィカルさんは実は数日前から、「契約の時に騙されないか」と心配していた。これまでに「外国人だからわからないだろう」と、給料を約束通り支払われなかったり、貸した金を返してもらえなかったりといった不信の蓄積があり、シビアな状況下でその記憶が彼の脳裏をはいずりまわっていたのだ。A社長はそんなことしないと安心していたが、不動産の売買は日本人でも理解しづらいことが多いし、ましてや自分のお金ではない。プレッシャーはとんでもないものだったはずだ。
そして迎えた、2月16日15時。私はこの日を忘れもしない
A不動産の前には、ジャケットを身にまとい、ビジネスマン風の手提げカバンを持ち、奥さんと立つフィカルさんの姿があった。その日はあまりに寒い日だったので、私と奥さんとカメラマンのI氏は駐車場で集合し、すぐに不動産屋の中に入った。しかし挨拶をしても、反応がない。重い沈黙が走ったが、しばらくすると「ドタドタドタ!」と、大きな音がして奥の階段からA社長が下りてきた。彼も珍しくスーツ姿だ。初めて通してくれた2階への階段を上がると、奥のソファに不動産会のドンであるS社長が鎮座していて、その横に今回の物件の契約のために動いてくれたA社長の先輩もいた。
「いやー、よく貯めたねえ。すごすぎるわ」
こんなに早く実現するとは誰も思っていなかったと、社長たちも心底驚いている。カメラマンI氏は、歴史的契約の瞬間を撮影しようと準備をはじめた。パンデミック中にインドネシア人コミュニティを追いかけ、モスク誕生の契約を撮影した異教徒は世界広しといえど、きっと私たちだけだろう。
この日は契約書をまとめサインをするが、また後日に銀行で集合する。売り主を加えたこのメンバーが立ち会い、その場で売り主の口座に送金する手順だ。
フィカルさんは彼らと対面するようにソファに座り、カバンから分厚い封筒を2つとりだしてテーブルに置いた。その中には270万円の札束が入っていた。高さ10センチくらいはあるだろうか。札束の枚数を数える機械にいれると、モーター音と札がこすれる音が室内に響く。
「しっかり270万円あるね」と、ドンが機械の目盛りを確認した。
これは手付金だ。通帳を見せ、資金が貯まったことを確認してもらい、契約書に押印とサインをしていく。一般社団法人の「KMIK」のハンコを押したあと、「フィカル」とカタカナで記す。その繰り返しが書類6枚で行われた。ハンコを押すたびに、これまでの苦労や事件を思い出す。家族や子どもとの時間も犠牲にし、レッドブルを頼りに休みなく動き回ったあの長大な時間と労力を思うと、たったこれだけで契約に至るのが不思議に思えた。
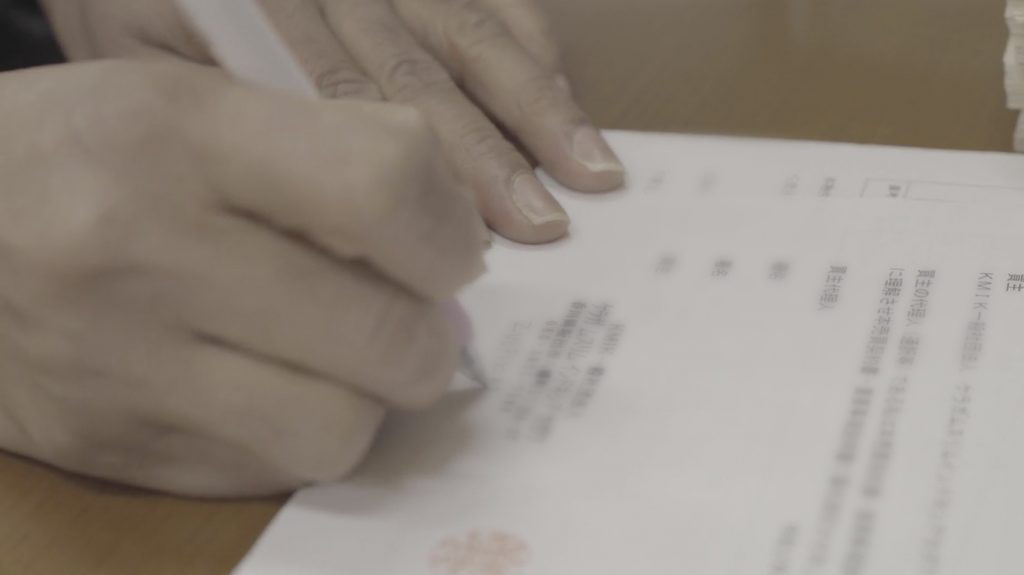


「お疲れ様。あとは銀行に行って、売り主さんに代金を振り込んでもらえば、終了。あと、もう少しだね」
その日程に3月1日を提案されると、フィカルさんは「いやそれじゃ遅すぎるね、2月の早い時期に契約したいね」 と言う。社長たちは驚いていた。「3月中にメンバーのうちの2人が帰ってしまうけん。絶対それまでに完成させて、 そこでお別れ会したいね」。
KMIKきっての人格者であり、功労者であるアディさんが今年の3月に母国へ戻ることになっていた。「私がいるうちに完成しなくても、いいですよ」 とアディさんは言っていたが、フィカルさんはみんなで喜びを共有したいのだ。
ついにやってきた、待ち焦がれた瞬間。まさかの代筆の重み
2月24日の午前11時。モスクが誕生する日である。私は、銀行での送金の際の通訳として、ついていくことになった。X市の小さな銀行の中に入ると奥のドアが半分開いており、そこにA社長、ドン、他にも3人ほど見知らぬ日本人がいた。ソファに座り談笑しているが、フィカルさんだけは沈黙を守っている。私が座ると、そのうちの一人の男が名刺を差しだした。司法書士だという彼が書類の諸々を手伝ってくれる。対面に座る初老の夫婦が建物の持ち主で、売り主のようだ。フィカルさんと会話をしないどころか、顔を見ようともしなかった。
A社長が場を取り仕切り、購入の説明がはじまった。購入後にかかる税金の話になると、フィカルさんは少し怪訝な顔をし「それはなんですか?」と聞く。インドネシアではそんな税金はかからないので、不審に思ったようだ。いやー本当に、海外で物件を購入するのは大変だ。
そんなこんなでやっとすべての手続きが終了し、ついに売り主への送金の瞬間が訪れた。銀行員が3枚の振り込み用紙を持って部屋に入ってくる。「振り込み代がかかるからね」とA社長。「いくらですか?」と聞くフィカルさん。880円という安値だったが、不信感を抱くフィカルさんを気遣ってか、A社長の先輩が財布から無言で支払ってくれた。
振り込み用紙には代金だけではなく、住所も書かなければいけない。フィカルさんは漢字を書くのが苦手だ。彼に代わって、住所や連絡先、金額も私が書くという大役を任されることになってしまった。これまでの苦労を知る私は、緊張で手元がこわばる。
7人のおっさんたちが私の手元を注視する中、まず1枚目に230万円と記入。これは土地代だ。2枚目に、150万円。これは不動産屋さんたちに支払う手数料。さらに住所と名前を書き込む。そして、ついに3枚目の建造物の入金へ。「2、3、0、0、0、0、0、0円」と、用紙に書き込むときがきた。私は息を飲んだ。ペン先を落とす。集中しているからか、インクがペン先から染み出ていくのがわかった。これはただの数字ではない。全国のムスリムの純粋な信仰心の集合体だ。KMIKのメンバー、フィカルさん、会ったことのない技能実習生たちの夢。手が震えた。ペンが重い。私は、これまでにない圧の筆致と、慎重さで数字を書いた。イギリスのテレビで見た9.11の光景から20年、人生とは不思議なものだなどと思いながら。
最後の数字を書き終えたその瞬間、拍手が起こった。
「おめでとう。これでフィカルさんたちのものです。モスクができたね。ほんとに、ほんとに、お疲れ様」。A社長が、カギが20個ほどついたキーホルダーを渡してくれた。A社長、不動産会のドン、先輩、銀行員まで、拍手した。
私はミスなく書ききったことに安堵し、肩の力が抜けた。フィカルさんは、まだ実感がなさそうに、ふふふと笑みを浮かべ「ありがとうございます、社長たちのおかげね」と、握手を交わした。A社長にとっても大変だっただろう。不安定な社会の中、不動産界隈の大物とインドネシア人の間に挟まれ、意見のすり合わせをするのに気をもんだはずだ。私とて、世俗と信仰が地続きの彼らの金銭感覚や計画の進め方に、最初は戸惑った。このモスク誕生はA社長の我慢と忍耐のおかげでもある。
私は銀行の外に出て、大きく背伸びをした。まさか代筆するとは思いもしなかった私に、A社長は「来てくれて助かったわ。じゃ、またね」と言い残し、ママチャリで会社に戻っていった。
夢の成就。そして、念願の初祈り
ジョイフルのドリンクバーでコーヒーを飲み、定食を食べる。何回繰り返したかわからないことだが、私たちはお互い、放心状態になっていた。フィカルさんも、珍しく無口だ。
疲れ切っていて「普段使わない言葉ばかり。頭痛いね」とつぶやいた。次々とメールの着信音が鳴る。KMIKの仲間たちからだろう。グループチャットを見せてもらったが、インドネシア語と感涙の絵文字が、いくつも並んでいた。「なんてかいてあるの?」と聞くと、「兄さんの夢が叶うね、って」。「夢ってなに?」「寄付がうまくいかんで、しんどいときに、みんなに言うたんや。これだけいいことしたら、みんな天国行けるね。みんな技能実習生や学生だから、そのうち離れ離れになるけど、みんなで天国で会うのが夢やって」
そう言って、フィカルさんは、下を向いた。きっと涙を必死で抑えているのだろう。


「岡内さんもそうよ。死んだ後も天国行けるように、いつも祈ってますよ。そしたら、あっちでも遊べるやん」
かつてこれまで私のことを祈ってくれた友人がいただろうか。天国があるかはわからないが、私は救われた気がした。私も笑って死ねるかもしれない。長年まとわりついていた、いつもなにかに追われているような感覚が一瞬だが消えた。
フィカルさんは、抑えていた感情が徐々にこみ上げてきているようだった。「やっと実感湧いてきたね」と、いつもの柔らかな憎めない笑顔を見せ、ぺらぺらとよくしゃべりはじめた。そして私を見つめ、こう言った。
「モスクにいきましょう」
さらっとでてきたこの言葉。存在していなかったモスクが、いまこの一言で、香川県に生まれたのだ。
車をモスクの駐車場に止めて玄関へと向かい、もらった20個ほどのカギを一つひとつ試していく。これでもない、あれでもないと5分くらい試すとやっとドアが開いた。一階はがらんとした倉庫のような大部屋、2階は小さなキッチンやトイレなどがあり、その奥に長方形の元事務所がある。白い壁の無機質な部屋を見て、少しわいたモスクが生まれた実感がまた消えた。かつてのキーボードを打つ音や、商談の声、部下を叱る怒声などが、一面にへばりついている。相変わらず世俗的で、神々しさのかけらもない。だがフィカルさんは気にも留めていない。
「私ね、初祈りはひとりでしたいって決めとったんや。ほんまは、みんなでしたほうがいいってわかってるけどな。これだけ頑張ったんだから、みんな許してくれるね」
フィカルさんはお祈り用の絨毯を前方の左隅、窓際に敷いた。日暮れの時間。夕日が窓からさしこんでいる。私は隅っこに座り、フィカルさんが足や手、顔を水で浄化するのを待った。部屋に戻ってきたフィカルさんは、顔と髪、足やひじをほのかに濡らしたまま、見たことがないくらい爽快な笑顔だった。これがやりきった男の顔か。眉と目じりをたらし、澄み切った眼をしている。堂々とした歩調で絨毯の上へと歩き、メッカの方向へ向かい、祈りがはじまった。私は隅っこに座り、静かに見つめた。オフィスは、アラビア語の詩句と、夕暮れの光に美しく輝いた。
ビスミッラーヒル ラハマーニル ラヒーム
(慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において)
アルハムドゥ リッラーヒ ラッビル アーラミーン……
(万有の主、アッラーにこそ凡ての称讃あれ)……
ゆっくりと時間が流れ、夕日の閃光がだんだんと窓の下に落ちていき、夜更けに近づいていく。たった5分ほどのお祈りだった。が、その間にも太陽や地球や月は宇宙の法則のうえで動いていることを感じさせる。彼にいま、どんな感情が去来しているのだろう。いつもの祈りとは何か違うものがあるのだろうか。どれほどの尊敬と感謝を神に示すのか。私には想像がつかない世界だ。
・
「アッラーアクバル(神は偉大なり)」
・
その言葉の後、絨毯に座る男がひとたび額を床につけた瞬間に、私は稀有な空間の変容を見た。世俗的なオフィスが、ゆっくりと聖のベールをまとっていくように見えたのだ。やわらかで羽衣のようなベールとともに、生々しい神の気配を感じた。私が見てきたほんの2年間の歴史の文脈が、この祈りの意味を重厚にしたのは間違いない。しかし、本当にここが聖なる場所に変わったと感じた。
100年後、200年後、さらにその先、次々と人が入れ替わりながらここはモスクとして機能し、日々の祈りが蓄積されていく。その歴史は、ある男の祈りからはじまった。私はその聖なる出発点を見ていた。
次回、最終話。「これから」
















