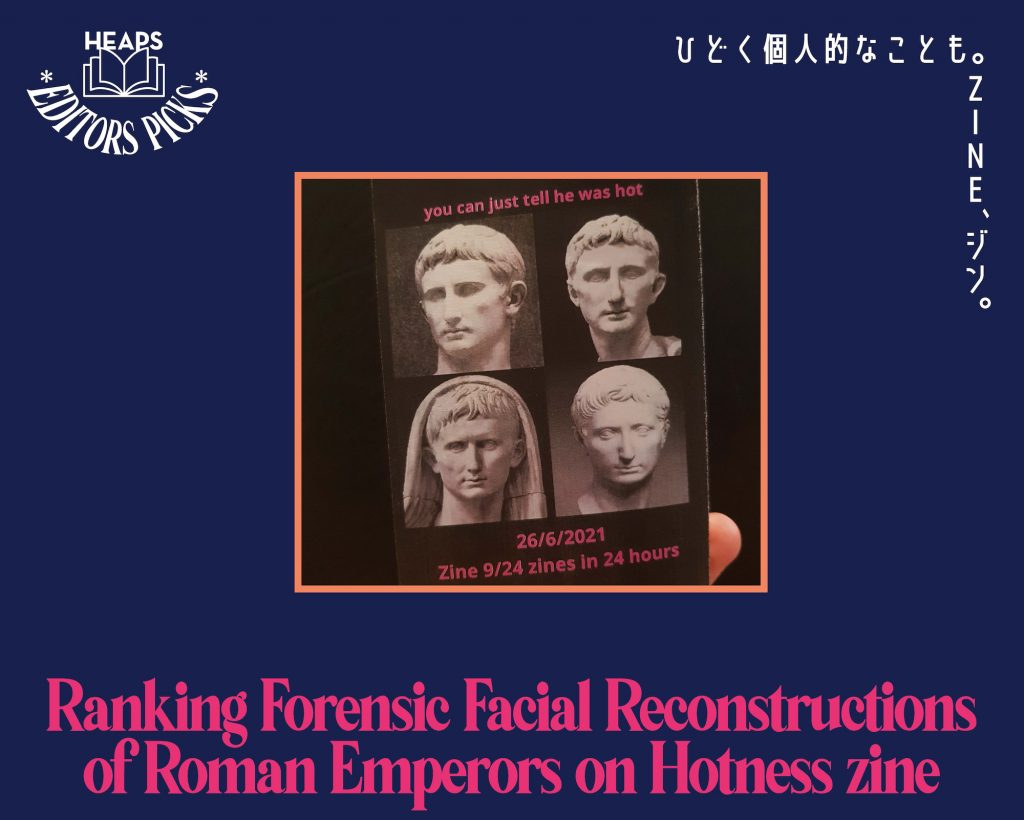「人々の行動をデザインの力でより良く変えたい」
犯罪の多発で評判が地に落ちたニューヨークの地下鉄の信頼を甦らせた日本人デザイナーがいる。彼の名は宇田川信学(49)。空間デザインとは、人を導くデザイン。してほしい行動を促し、してほしくない行動を抑制する。デザインの力を“武器”に宇田川が手がけた地下鉄車両は、ニューヨークの地下鉄内で起こる犯罪の軽減に貢献した。「人々の行動をデザインの力でより良く変えたい」と語る宇田川の挑戦に迫る。
長く厳しい冬から春の陽気に変わり、観光客の姿がそこかしこに見られるようになったニューヨークのギャラリー地区、チェルシー。毎週のようにギャラリーで展示会が開かれる刺激的な街の一角に、工業デザイナー宇田川の事務所がある。自らデザインしたシンプルなデスクと広々としたオフィス空間が、ニューヨークにすっかりとけ込んだデザイナーという印象を与える。アメリカ人の間でも見劣りしない長身の宇田川はそこで、ニューヨークの環境と人々を変えることになった二つの大きな仕事について静かに語りはじめた。
デザインの焦点は、使う人の気持ち
地下鉄に関わる最初の仕事は、メトロカードと呼ばれる乗車券の自動券売機のタッチパネルの表示をデザインすることだった。依頼があった1999年当時、アメリカでは自動券売機そのものが珍しく、地下鉄の運営会社が「人々に受け入れられる券売機」の開発でデザイナーに協力を求めた。宇田川がデザインのヒントにしたのは、人々の日常生活だった。
宇田川は、買い物で客と店が交わす会話のスタイルをヒントに、「どの言語を使いますか」、「カードの種類を選んでください」など、タッチパネルに簡単な質問や指示が表れるデザインを考案した。分かりやすさを追求し、画面に一度に表れる質問や指示は一つに絞った。また、ニューヨークでは公衆電話が壊れていて使えない、料金を支払っても機械が動かないことなどは日常茶飯事だった。そのため、使用者の公共物に対する信用が薄い。それを熟知していた宇田川は、支払いは最後にする手順までも計算した。「自動券売機になじみのない人にいかに使ってもらうか、その観点ですべてをデザインしました。デザインはものをつくるというよりも、使う人の思い、要望を形にすることだと思っています」人をデザインの中心に置くこと―。公共スペースから家具といった商業製品まで幅広く手がける宇田川だが、すべてのデザインの根底にはこのぶれない基本姿勢がある。
地下鉄の車内空間をデザイン、犯罪抑止へ
次に宇田川が受けた依頼は、ニューヨークの一つの象徴であり、この街のネガティブな側面をも代表する地下鉄車両の車内空間をデザインしてほしいという仕事だった。運営会社は、1970年代に悪化したイメージや犯罪率軽減の改善策として車両の刷新を進めており、内部デザインにいたっては、単純な装飾や快適性以上に、車両内犯罪を軽減するための具体的な策が求められていた。宇田川は、責任と面白みの両方を感じたという。日本とはかけ離れたニューヨーク独特の地下鉄での犯罪や人々の行動を理解する必要性と、自身が信じるデザインの力を試す機会。「物の形や機能には意味があり、人々はその意味を受け取って行動を起こす。それは無意識だったり、時には犯罪に結びつくこともある。つまりデザインによって『してほしい行動』に人々を導いたり、『してほしくない行動』を防ぐこともできると思っています」
宇田川はまず、自身の目で徹底的に地下鉄を見て回ることに決めた。繰り返し、いろいろな時間帯に、いろいろな路線に乗り込んだ。朝、昼、夜、深夜と、24時間運行の中で次々と変わる混み具合や客層を確認した。多様な移民街を反映して路線によって異なる車内の雰囲気も肌で感じ取った。グラフィティと呼ばれる派手な落書きをどう落とすのか、ナイフや工具で故意につけられる傷をどう防ぐのか。具体的に知るため、郊外にある修理工場にも足を運んだ。
その結果、宇田川は、塗料の落としやすさから壁など広範囲の表面に導入されていたステンレス素材に注目した。80年代にステンレス素材が導入され、落書きは減っていったものの、今度は新たに、ひっかき傷をつける行為が問題化していた。「ステンレスだと同じ量の照明を使っていても車両内が暗く見える欠点もあります。入ったときに『明るい』と感じられれば、落書きや傷をつけるような振る舞いがなくなるのではないかと」。代わりに、壁は白を基調にした樹脂素材に、床は滑りにくい黒色の天然ゴム素材にすることで、明るく、広く感じられるようにした。
さらに、壁材、床材両方に、御影石のように細かな粒子を混ぜて汚れが見えづらくなるように施した。また、駅のプラットホームから手を伸ばして鞄をひったくるなどの犯罪を防ぐため、ドア近くの座席側面に取り付けるステンレス素材の防護バーをデザインした。警察からの要請で、当初は防護バーではなく、防弾ガラスのつい立てを考えていたが、「ひっかき傷をつける格好のキャンバスになってしまう」と急な要請にも応え変更した。防護バーには段があり、はしごのような印象を子どもたちに与えて登らせないよう配慮し、傾斜をつけた。2013年、宇田川は「過去25年間で最も影響力のあるニューヨーカー100人」に選ばれた。2000年から走り出した“宇田川デザイン”の車両は、小規模な変更を繰り返しながら現在、6路線以上で約4,000台走る。最終的にはニューヨークを走る地下鉄車両約6,000台すべてが宇田川の車両になる予定だ。
ミリタリー少年、大学で工業デザインに出会う
東京で育ち、幼いときはプラモデルの戦車や戦闘機をつくるのが好きな工作少年だった。今振り返ると、そのころ触発された形や線、その機能こそが、デザインとは何かの原点として記憶に刻まれているという。「ドイツの戦闘機はイギリス機に比べて直線が多いんです」と楽しそうに話す宇田川。「その国の文化によって物の形が違うのだと学びました。新しい素材の開発で戦車の形状が変わっていく様子も面白かった。そうやってなんとなくデザインに興味を持ったのだと思います」
しかし、工業デザインとの出会いは、実際には偶然の産物だった。「けっこう行き当たりばったりの性格なんです」と話すように、大学受験の際、当初の志望は建築学科だったが、「入学しやすそう」という理由でデザインについて学ぶ千葉大学工業意匠学科に専攻を変えた。「『工業意匠学科』という名前にも惹かれました。実際はその学科が何をやっているのか知らなくて、入学した後に分かりました」と苦笑しながら打ち明けた。人生を変える出会いは、大学卒業前にも訪れた。後に留学することになるミシガン州にある大学院クランブルック・アカデミー・オブ・アートを卒業した日本人デザイナーの講演が大学であり、そこに通う学生の実験的なデザインに衝撃を受けた。当時、製品や物の世界はデジタルの領域に入りつつあり、機能主義的なデザインを超えて、物の「意味」を形にする手法が注目されはじめていた。「あそこに行かないといけない」。留学したいという夢は大学卒業後に音楽機器メーカー「ヤマハ」に入社しても消えず、2年半で退社して渡米した。大学院を卒業後、ニューヨークのデザイン事務所やサンフランシスコのアップル社のデザイングループなどを経て、ニューヨークで、パートナーと共に、現在のデザイン事務所「AntennaDesign」を立ち上げた。
失敗したときは、最初の目的に立ち返る
2006年、アメリカの老舗家具メーカー「Knoll(ノル)」との共同開発でオフィス家具のデザインもはじめた。個人の好みや部屋の個性に合わせて机や収納スペースのパーツを自在に組み合わせ、快適なオフィス空間をつくるシステム家具といわれるもので、様々なパーツと、組み合わせのロジックをデザインする。宇田川は当初、使い方に融通が利くことを第一にした。気がつけば、2008年の発売予定日まで残り半年。その時、問題が起きた。機能性を上げるために、組み合わせる作業が複雑なものになり、パーツの数が増えすぎていた。生産しにくい、と工場から苦情が出て、販売価格も予定よりオーバーしていた。どうすればいいのか。宇田川は悩んだ。1年半かけてデザインした商品。こだわりが詰まっているが、問題が出ている。宇田川は、目指すデザインの定義に立ち返った。「つくりたいのは、柔軟に使える家具。そのためには複雑すぎてはいけない」
宇田川は、それまでに考えたデザインをいったんゼロに戻すことにした。発売も延期し、2年後の2010年、パーツの数を少なくしたシンプルなシステム家具を発表した。価格も前回より低く抑えた。デザインの方向性を間違えたことについても、冷静に振り返る宇田川。しかし、そこでぽつりと本音をもらした。「半年、1年と長い間、正しいと信じてやってきたことをやめるのは心情的に受け入れがたいですよ、本当は。でもね、ある時吹っ切れます。間違ったときは素直に『間違った』と認めて、先に進むことが肝要ですね」。地下鉄車両デザインの際にも、実は似た問題にぶつかっている。座席側面に防弾ガラスのつい立てを取り付ける計画で長く進めていたが、ひっかき傷の問題に気づいて直前にデザインを変更した。「人々を犯罪から守り、またひっかき傷などの犯罪を誘発させないデザインをする」という目的に立ち返った例の一つだった。
日本人として、「恥ずかしくない仕事を」
オフィス家具の仕事は、日本の価値観を見直す良いきっかけにもなった。少ない素材に多くの機能をもたせ、エレガントに仕上げる手法はどこか日本の伝統的な美意識に通じる。宇田川は、良いデザインは「透明な存在」だという。「うまく機能しているときには誰もその存在を気にしない。特に公共スペースのデザインは毎日使うものなので、気づかれないほどさりげない存在でいい」日本の価値観、特に父親から教えられた古き良き「職人」の価値観も大切にしている一つだ。地道にものごとに取り組むこと。まじめさを忘れないこと―。
地下鉄の車両内部のデザインでは、運営会社から警察、清掃担当者、乗客を代表する市民団体と関係者が多く、全員の要求をデザインに盛り込めなかったり、要求がぶつかり合ったりすることもあった。宇田川は、全員の意見を聞きに回った上で、「あなたの意見は分かります。ただ、それとは別にこのような理由があってそれとは違うデザインを選びました」と真摯な姿勢でプレゼンテーションした。合意形成に時間をかけ、丁寧に説明し、そして最後は自分のアイデアを信じる。それが、宇田川を良く知る周囲の人が「いい意味で頑固」とみるゆえんだろう。「日本人として恥ずかしくない仕事をしたい」。ニューヨークに来て19年。最近は、こうも思うようになったという。
デザイナーとして着実にキャリアを積み、数々の受賞歴にも輝いた。ニューヨーク近代美術館(MoMA)には、地下鉄の救援・案内システムとして設計した通話装置「ヘルプポイントインターコム」がコレクションされた。年内には、首都ワシントンD.C.の地下鉄にも自身がデザインした車両が登場する予定だ。けれど、いずれも通過点に過ぎない。「デザインも人生も長丁場。まだまだ、新しいことができる」。おごらず、根気よく、そして仕事仲間やパートナーとともに楽しく日々を過ごす。走るのは一人だが、同じ志を持った多くの仲間がいるランナーのように、宇田川は今日もニューヨークで自分の道を歩み続けている。

掲載 Issue 15