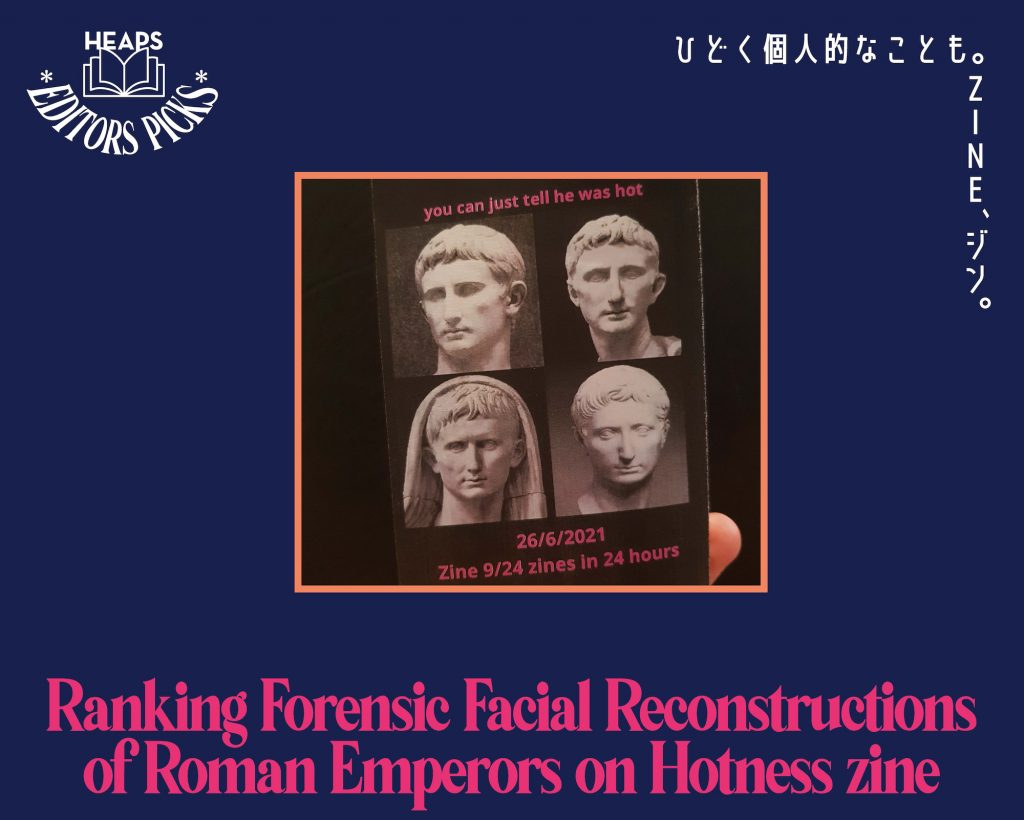チカ、チカ、チカ。振り返ってシャッターを切った。何度目かでバスを待っていたその男とファインダー越しに目が合う。「この男の顔。取り憑かれたような猜疑と静かな反抗。シチリアのパレルモという街の表情そのものだと思った」

©Mimi Mollica, Terra Nostra
多くの賞を受賞する写真家ミミ・モリカ(Mimi Mollica)が、個人のプロジェクトとして7年の歳月をかけて撮ったのは、かの悪名高きイタリア、シチリア島のマフィア、コサ・ノストラ(Cosa Nostra)があらゆる犯罪行為で散々に崩壊させたパレルモという街のその後、つまり現在の姿だ。マフィア勢力が去ってからも、その支配は続いている。血の滴る惨劇は過ぎたが、血の跡は静かに街にこびりついている。パレルモはミミが20歳で去った故郷だった。
見えない暴力、消えない支配
70年代にパレルモ含めシチリアで生まれるということは「生まれながらにしてマフィアのいる生活を知ること」。ミミは75年生まれ、その年は写真家レティシア・バタグリアが拡大するマフィアの犯罪行為と抗争をおさめた記録、An Archive of Blood(血の記録)を撮りはじめた翌年でもある。固い約束ごとのように必ず一日に一件は殺人があった。両親や周りの大人からマフィアについて教えられる必要はなく、言葉や遊び方のように「誰もが自然に覚えることの一つだった」とミミは言う。小学校では身の振り方も教わった。マフィアの存在が当たり前のように馴染んでいた生活。それが、パレルモの日常だった。

©Mimi Mollica, Terra Nostra
93年、コサ・ノストラのボスであったサルヴァトーレ・リイナの逮捕がドミノ倒しの大きな一手となり、勢力は一気に失われるが、その時までシチリアはマフィアによって徹底的に支配された。政治と密接な関わりを持ちあらゆる行政に入り込み、市民生活にまで影響を及ぼした。支配の晩年を追っていた記者は「あらゆる戦場の特派員を経験したがこの時のパレルモこそ最も怖かった」と語っている。状況はだいぶ改善されているとはいえ、9割のローカルビジネスが恐喝罪の対象になる地域もいまだにある。
映画で描かれるマフィア像の嘘

©Mimi Mollica, Terra Nostra
ミミが20歳でパレルモを去ったのは1996年のこと。「自分が得られるべき機会はこの街にはないと思ったから。すでに限界が見えるような人生で窮屈だった。きつすぎるジーンズを履かされたみたいに」。ロンドンに行き着き世界を旅し、写真家としていくつも賞を受賞した後の2009年、壊れされた故郷パレルモを撮りはじめた。その街に残っている暴力の残滓を「当時の暴力の現場ではなくて、」散々な暴力が残していった“遺産”として囁やくようなニュアンスで伝えたい、と。確かにマフィアは去ったが、この社会で自分はどう振舞うべきか、人とどう関わるべきか、何を信じるのか、そういった生活の根源的な各所にマフィアがいた、という影響が残っている。
「たとえば拳で殴るなどのフィジカルな暴力は避けたり防いだり、あるいはやり返せる。だが、その“暴力による影響”というのは見えないから避けられない。ある意味で、暴力によるよりひどい惨劇は静かに、後に残って人を蝕んでいくものだ」。
暴力とはまさにその瞬間にこそ残虐性を露わにするが、一過性でなくその瞬間から続いていくものなのだ、と写真を通してつきつけた。喉元を過ぎて忘れても、本人さえ気づかない程度に皮膚の下でチリチリと焼け続けているようなニュアンスで。
街のあちこちに残る銃弾の跡、憩う家族の後ろにそびえる壊れた建物。こんな街でどうせ、と無意識に緩やかに人生の希望を削いでいくような停滞した街。ここにはいまはモノクロが似合うと思って、と7年間、その街の影と光を写した。大量の写真から最終的に60枚まで絞り一冊にまとめ、今年2月に出版した。



©Mimi Mollica, Terra Nostra
「米国映画の魅力的なマフィアみたいなもんじゃないよ。一つの島を壊すだけの暴力は惨劇でしかない」。そしてその惨劇は、まだ静かに続いている。だが、島の住民よりも少ない人間に壊されたのだから、ここに暮らす人々が結束したら取り戻せるんじゃないか、とミミは思っている。
コサ・ノストラ(Cosa Nostra、我々のもの)に壊されたこの街が、再びTerra Nostra(Our Land、我々の土地)になるようにと、写真集にはそうタイトルをつけた。「できれば自分が生きているうちに」。その時がきたらミミ・モリカは、美しいシチリアの島と街をカラーで鮮明におさめるだろう。どの海よりもシチリア、パレルモの海を青く。

©Mimi Mollica, Terra Nostra
Interview with Mimi Mollica
Terra Nostra
Text by Sako Hirano
Content Direction & Edit: HEAPS Magazine